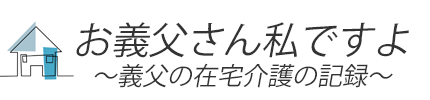認知症の方の在宅介護のコツとは

負担の原因を知って対策を立てる
在宅で認知症の方を介護するには、家族の心身に大きな負担がかかりがちです。突然怒り出したり、寝ている間に徘徊をしたりと、想定外の行動が続くことで介護者が疲れやすくなります。こうした負担の原因としては、記憶の混乱による意思疎通の難しさや、日常生活の介助における不規則な睡眠時間などが挙げられます。さらに、ご本人の不安定な気持ちが表情や言葉に出ることで、家族も気持ちが揺さぶられるケースも珍しくありません。
まずは、介護者自身が抱える疲れやストレスを自覚することが大切です。心の余裕を保つためには、周囲のヘルプを得られる体制を整えたり、デイサービスなどの外部サポートを適宜活用したりすることを考えてみてください。また、認知症の進行度や特性を理解し、ご本人の視点に立って接することも負担軽減につながります。
ボディメカニクスの活用で身体的負担を減らす
認知症の方を介護する場面では、食事や入浴、排泄介助など、身体を支える動作が多くなります。そこで活用したいのが「ボディメカニクス」という考え方です。これは、身体を効率よく動かすための原理を応用し、介助する側とされる側の負荷を最小限に抑えるテクニックを指します。
たとえば、抱え上げるときは自分の腰を落として重心を低くし、ご本人と身体を近づけて支えるようにすると負担が軽減されます。また、相手の体重をできるだけ分散させるため、広い面積で触れることもポイントです。ボディメカニクスを意識するだけで、腰痛や肩こりなど介護者に多いトラブルを予防しやすくなります。いくつかの基本的な姿勢や動作を習得するだけでも、日々の介護が格段に楽になるでしょう。
日常生活でのコツやテクニック
認知症の方は、自分の言葉で意図を伝えるのが難しくなることがあります。そのため、介助をするときは一度に複数の指示を出さず、短いフレーズでゆっくり伝えることが大切です。例を挙げると、食事に誘うときは「一緒にご飯を食べましょう」と声をかけながら、食卓にゆっくり誘導するなど、状況をシンプルにしてあげる工夫が有効です。
また、ご本人が不安定になったときは、過剰に否定したり説得したりせず、「そうなんですね」といった受け止める言葉を先にかけてみてください。気持ちを落ち着かせることで、次の行動へ移りやすくなります。さらに、生活リズムを整えるためには、軽い運動や外出の機会をつくり、昼夜逆転を防ぐことも意識すると良いでしょう。こうした小さな工夫の積み重ねが、認知症の方と介護者双方の負担を軽減する大切な鍵になります。